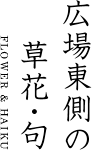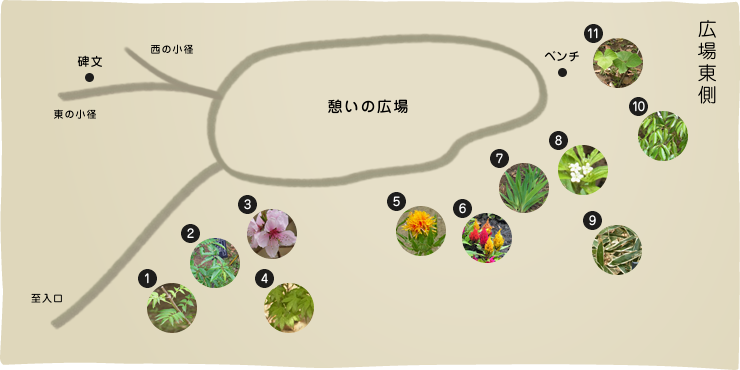
ニワトコPieris japonica subsp. japonica
| 万葉呼名/やまたづ | 分類/スイカズラ科落葉低木 | 開花時期/2~4月 |
「君が行き 日(け)長くなりぬ やまたづの 迎へを行(ゆ)かむ 待つには待たじ」軽太郎女(巻二・九〇)
*あなたが旅立ってから随分と長い日が経ってしまった。お迎えに行こうか。もうこれ以上待つことなどできはしない。


ニワトコは早春にいち早く芽吹き、花は4月ころまで泡花が吹き出したように咲く。「接骨木」とも書き、古くから民間薬や漢方薬として親しまれている。『万葉集』には、「やまたづ」が詠まれているのは2首だけで、もう1首は高橋虫麻呂の長歌である。葉が向かいあってつくことから「やまたづ」は「迎へ」の枕詞。
この歌の題詞に「古事記に曰く軽太子(かるのひつぎのみこ)、軽太郎女(かるのおほいらつめ)に奸(たは)く。この故にその太子を伊予の湯に流す。この時に衣通王(そとほりのおほきみ)恋慕(しのひ)に堪(あ)へずして追ひ往(ゆ)く時に、歌ひて曰く」。
軽太郎女は、衣通王(彼女の美しさをほめる通称)ともいい、軽太子とは同母兄妹。昔は異母兄妹・姉弟の恋や結婚は普通に許されていたが、同父母の恋愛は現代と同様タブーとされてきた。掟破りの二人の悲恋は、軽太子は廃太子となり、伊予の道後温泉へ流罪となった。
「君が行き」の君は軽太子をさし、軽太郎女の諦めきれない悲痛な叫びが胸打つ。それを軽太郎女が追いかけていき、そして、結末は心中・・・・・。
類似歌はヒオウギで紹介する。
クリRhododendron kaempferi
| 万葉呼名/くり | 分類/ブナ科常緑高木 | 収穫時期/10月下旬~ |
「瓜食(は)めば 子ども思ほゆ 栗食めば まして偲はゆ いづくより
来りしものそ まなかひに もとなかかりて 安眠(やすい)しなさぬ」山上憶良(巻五・八〇二)
*瓜を食べていても、栗を食べていても子どものことを思わないときはない。子どもというものはどのようなことで来たものであろう。目先にちらついて、私は安眠できない。

当時、瓜といえば古くに中国経由で渡来したマクワウリをさし、口にするには贅沢品だったようだ。栗は、縄文時代には日本で自生しており、実は食料に、木は建築、造船などに使われた。
山上憶良は40歳を過ぎてから遣唐使として唐へ渡り、儒教や仏教などの学問の研鑽に努めた。33年ぶりに再開されたこの遣唐使の一行に選ばれたのは、彼が百済国滅亡による朝鮮からの渡来人だった(4歳にして祖国を失った)からとの説がある。それから20数年後筑前国守に任ぜられ下向。かの地で太宰の帥(そち)として大宰府に着任した大伴旅人や小野老らと筑紫歌壇で活躍した。まもなく任期終えて帰京。深い見識と知性、情感で、官人でありながら、妻子や貧しさに喘ぐ農民など社会的弱者を観察した歌を数多く詠んだ。大伴家持、柿本人麻呂、山部赤人らと共に奈良時代を代表する歌人と評される。
反歌として、「銀(しろがね)も 金(くがね)も玉も 何せむに 勝れる宝 子に及(し)かめやも」山上憶良(巻5-803)がある。
モモPieris japonica subsp. japonica
| 万葉呼名/もも | 分類/バラ科落葉低木 | 開花時期/3月初旬~ |
「春の苑 紅にほふ 桃の花 下照る道に 出で立つ娘子」大伴家持(巻一九・四一三九)
*春の苑は紅に染まっている。桃の花が輝く道に出で立つ乙女よ。

「にほふ」は本来「香り」をいうが、この歌では目に見える色あい、つまり輝くモモの紅色を意味している。この木の下にたたずむ乙女は実景ではない。
このころ、家持は越中(富山県高岡市)の国守として赴任しており、同族の大伴池主(おおとものいけぬし)らと交流し、日本海を望む越中の風土の中で、朝鮮半島や中国文化に思いを馳せ、平城京で暮らしていたときよりも旺盛な作歌活動を展開している。都での政権争いから離れて、家持にとっては「よき時代」だったのかもしれない。
モモは古代(縄文時代末期~弥生時代)に中国から渡ってきた果樹であるが、災厄から逃れさせてくれる「仙木(せんぼく)」としての役割が大きく、薬草としての効果が信じられていた。
いわゆる「越中秀吟」十二首の題詞「三月一日の暮(ゆふ)に、春苑の桃李の花を眺(てい)しょくして作る2首」の一首目が桃の花の歌。二首目を紹介しよう。
「吾が園の 李(すもも)の花か 庭に降る はだれの未だ 残りたるかも」
大伴家持(巻19-4140)
-我が園の李の花か、それとも庭に降った斑雪(はだれ)がまだ残っているのか-
幻想の乙女、幻想の斑雪など色や光を鋭く捉えるのが、家持の本領なのである。
ヤマモミジRhododendron kaempferi
| 万葉呼名/もみち | 分類/カエデ科落葉高木 | 紅葉時期/10~12月 |
「経もなく 緯も定めず 娘子らが 織るもみち葉に 霜な降りそね」大津皇子(巻八・一五一二)
*縦糸も横糸も決めずに、乙女たちが織る紅葉の錦に、霜よ降らないで。

万葉歌では、紅(赤)や黄色に色づきはじめた美しい秋の風景や、時雨(しぐれ)て散ってしまわないかと惜しむ気持ちなど、さまざまな心模様が数多く詠まれている。
奈良時代にはモミジを「もみち」と清音で読み、「もみぢ」と濁音化するのは平安時代以降のことである。
『万葉集』には大津皇子(おおつのみこ)の歌は4首掲載されているが、2首は恋の歌(石川郎女への贈答歌)、1首は辞世の歌であり、残りがこのお歌である。おそらく、秋の宴席で歌われたもので、美しいモミジを織物に見立て、「どうか霜が降りませんように」と大津のやさしが滲み出ている。
幼いころから聡明で、人柄もよく血統的にも申し分のなかった大津が、24歳の若さで有能であるがゆえに、謀反の罪で処刑され「悲劇の皇子」として後世に伝えられるのである。
大津には2歳年上の同母姉の大伯(おおく、または大来)皇女がいる。ふたりは幼くして母(大田皇女、父は天智天皇)亡くしており、とても仲が良かったらしい。『万葉集』には大伯の歌が6首掲れているが、どれもこれも大津を愛(いと)おしむ様子が強く伺える。大津を葛城の二上山に移葬したときの弟に寄せた挽歌を紹介しよう。
「うつそみの 人にあるわれや 明日よりは 二上山を 弟背(いろせ)とわが見む」大伯皇女(巻2-165)
この世に生きているわたしは、明日からは二上山をわが弟と見ようか。
この歌には、大伯皇女が一人きりの弟に寄せる万感の想いがこもっている。
ベニバナPieris japonica subsp. japonica
| 万葉呼名/くれなゐ | 分類/キク科一年草 | 開花時期/6~7月 |
「よそのみに 見つつ恋ひなむ 紅の 末摘む花の 色に出でずとも」作者不明(巻一〇・一九九三)
*知られないように遠くから無表情で恋していよう。いずれベニバナのように花のあとで紅鮮やかに染め上がる。今顔色に出さなくても。


アフリカ原産で古くから染料として各地で栽培され、日本には飛鳥時代に中国から渡ってきた。アザミに似た黄色の花をつけ、やがて紅色に変化していく。花の色素で布地を染める代表的な植物。種子から採れるリノール酸は動脈硬化によいとされる。ベニバナを「末摘花(すえつむはな)」とも呼ぶのは茎の末(下)の方から咲いていく花を順番に摘み採るから。このように人びとに身近な存在であったらしく、『万葉集』には29首も詠まれている。
『源氏物語』第六段「末摘花」は、光源氏が親友の頭中将(とうのちゅうじょう)と競い合った末に思いを遂げる物語だ。情事の翌朝、その女性の鼻の頭が「紅花のように末に赤い花(鼻)がある」と驚き、「末摘花」と綽名したのである。れっきとした常陸宮という皇族の一人娘であるが、美男美女揃いの『源氏物語』の異色の姫君だ。
「なつかしき色ともなしに何にこの末摘花を袖にふれけむ」―
慕わしいわけでもないのに、なぜにこの末摘花を袖に触れてしまったのだろうか―
興ざめした恋であったが、世慣れしない姫の風情を源氏はむしろ好ましく思い、また心細い身の上を哀れと思って、世話をすることに心を決めたのだった。源氏によりその後二条東院に引き取られ、妻の一人として晩年を平穏に過したという。
ケイトウRhododendron kaempferi
| 万葉呼名/からあゐ | 分類/ヒユ科一年草 | 開花時期/8~10月 |
「我がやどに 韓藍蒔き生ほし 枯れぬとも 懲りずて又も 蒔かむとそ思ふ」山部赤人(巻三・三八四)
*家の庭にからあゐを蒔いて、育てていたが枯れてしまった。また性懲りもなくまた蒔いてみようか。

山部赤人は奈良時代前期に活躍した宮廷歌人(聖武天皇のころ)だったと推測される。『万葉集』には、長歌13首、短歌37首が収められており、同時代の歌人には山上憶良や大伴旅人らがいる。たびたび天皇の行幸に供奉(ぐぶ)しり、また広く諸国(下総、駿河、伊予など)を旅していたと思われる。後世、柿本人麻呂とともに「歌聖」といわれた。
ケイトウ(鶏頭)の種子は光沢のある黒色の小粒。春に種を蒔き、夏から秋にかけて花が咲く。鶏のトサカに似て赤色をしているが、最近では黄色や紫、ピンク色も観賞用として出回っている。万葉の頃、ケイトウの花汁は、染料に用いられていたらしい。原産地が熱帯アジアやインドで、奈良時代に中国や韓国を経て渡来した。
この歌は、実際にケイトウの種を蒔いたのではなく、宴席で「韓藍」をお題にして詠まれていたようで、「韓藍」とは女性のこと。
つまりは、「私の家で美しい女性を住まわせていたのですが、その人は去ってしまいました。けれども懲りずにまた素敵な女性を探そうと思います」といった感じであろうか。
まあ、赤人にそのような想い人が実際にいたわけではないのであろうが、宴席での戯れ歌としては魅力的な恋歌だ。
現在の千葉県市川市真間で語り継がれてきた伝説の美女、手児奈(または手古奈、手児名)を詠んだ赤人の歌を紹介しよう。
「葛飾の 真間の入江に うちなびく 玉藻刈りけむ 手児奈し思ほゆ」山部赤人(巻3-433)
―真間の入江で玉藻を刈っていた美しい手児奈の姿が思い起こされる―
ヒオウギPieris japonica subsp. japonica 三木先生
| 万葉呼名/ぬばたま | 分類/アヤメ科多年草 | 結実時期/10月~ |
「居明かして 君をば待たむ ぬばたまの 我が黒髪に 霜は降るとも」磐姫皇后(巻二・八九)
*朝まで寝ないであなたを待ちましょう。私の黒髪に霜が降りようとも。

『万葉集』の歌の始まりは、5世紀前半頃の磐姫皇后(いはのひめのおおきさき)と言われている。磐姫は聖帝と称された仁徳天皇の皇后で、天皇の浮気に大いに悩まされ異常なくらい嫉妬深い女性だったと『古事記』や『日本書紀』に描かれている。「ぬばたま」とはヒオウギの真っ黒な実のこと。漆黒の実の黒さから黒いもの(黒髪)に続ける枕詞。
この歌は4首連作(題詞-皇后の天皇を思(しの)ひて作りませる御歌4首)の3番目の(巻2-87)の類似歌である。
「君が行き 日(け)長くなりぬ やまたづね 迎へか行かむ 待ちにか待たむ」(巻2-85)
「かくばかり 恋ひつつあらずは 高山の 磐根し枕(ま)きて 死なましものを」(巻2-86)
「ありつつも 君をば待たむ うち靡(なび)く 我(あ)が黒髪に 霜の置くまでに」(巻2-87)―このまま、あの方をお待ちいたしましょう。この長い黒髪が白くなるまで―
「秋の田の 穂の上(へ)に霧(き)らふ 朝霞 いつへの方に 我が恋やまむ」(巻2-88)
いずれも長旅に出られた天皇を待ちわびる気持ちを詠ったもので、現代では秀歌として評価されている。
ここで、たった数文字しか違わない歌をみてみよう。磐姫皇后(巻2-85)とニワトコ(やまたづ)で紹介した軽太郎女(巻2-90)だ。
「君が行き 日(け)長くなりぬ やまたづね 迎へか行かむ 待ちにか待たむ」磐姫皇后(巻2-85)
「君が行き 日(け)長くなりぬ やまたづの 迎へを行かむ 待つには待たじ」軽太郎女(巻2-90)
は、山上憶良が軽太郎女の歌を意識的に磐姫作に置き換えたとか、柿本人麻呂が編纂したとか、憶測が飛び交っている。
ムラサキRhododendron kaempferi
| 万葉呼名/むらさき | 分類/ムラサキ科多年草 | 開花時期/4~5月 |
「あかねさす 紫野行き 標野行き 野守は見ずや 君が袖振る」額田王(巻一・二〇)
*標野(御料地)の野を行きながら、あなたが袖をお振りにになるのを野守りが見てますわ。


かつては日本中に自生したいたムラサキだが、今では絶滅危惧植物の1つだ。花は白色の可憐な小花。根が紫色の染料や、火傷の特効薬として使われた。
668(天智7)年5月5日端午の節句に蒲生野(がもうの)で薬猟(くすりがり)が行われた。狩が終わって宵には宴がもうけられ、座興として歌われたのが、題詞―天皇(天智)の、蒲生野に遊猟(みかり)したまひし時に、額田王の作れる歌―とある、額田王の「あかねさす・・・」である。
その頃の宮廷は文化の中心であった。宮廷は華やかな遊びの世界であり、額田王は歌によって人々を楽しませる宮廷歌人であった。
袖を振るというしぐさは求愛のしるしで、今は天智天皇の妃のひとりとなっていた額田に大海人皇子が袖を振って見せた。それをたしなめた額田に大海人はすかさず、
題詞―皇太子(ひつぎのみこ・後の天武)答へし御歌―
「紫草の にほへる妹(いも)を 憎くあらば 人妻ゆゑに われ恋ひめやも」大海人皇子(巻1-21) あなたが人妻と知りながら、どうして恋したうことなどありましょうかと、天智の前で実に堂々と歌い上げたのである。
額田と大海人の秘められた恋のように思いたいが、近年の研究ではふたりの唱和は「座興のひとつに過ぎない」説が有力のようだ。
クマザサPieris japonica subsp. japonica
| 万葉呼名/ささ | 分類/イネ科常緑多年草 | 開花時期/ |
「笹の葉は み山もさやに さやげども 我は妹思ふ 別れ来ぬれば」柿本人麻呂(巻二・一三三)
*小竹(ささ)の葉は山路にざわざわと風に鳴っているが、わたしの心は今別れてきた妻を一途に思っているのだよ。

「ササ」はイネ科の竹亜科に属する植物でクマザサ、ミヤコザサ、ヤダケ、チマキザサ、ネガマリダケなどがその仲間。竹の中でも比較的小さいものを「ササ」と呼ぶ。「ささ(笹)」は小さい、細かいという意味があり、風に吹かれた葉の微妙な揺れや微かな音を「ささめく」、「ささやく」という。
種々の史書に柿本人麻呂に関する記載がなく、その生涯については謎とされている。その終焉の地も定かではないが、有力な説とされているのが、現在の島根県益田市(石見国)である。『万葉集』には87首、『柿本人麻呂(之)歌集』に370首もの歌があるというが、人麻呂作なのか否かも実は不明である。しかしながら、万葉歌人のなかでも優れた歌人の1人で、のちに「歌聖」と讃えられている。その生涯については、不明な部分も多いが持統天皇の時代には、宮廷歌人として活躍、律令制が本格的に機能始めた時期には石見(いはみ)の国国司として赴任している。
この歌は、任を終え都に戻る途中詠ったもので、妹(いも)は現地妻、依羅娘子(よさみのおとめ)と思われる。再び会うことがない別れに身を切られるような想いを綴ったのが、世に「石見相聞歌」として高い評価を受けている長短歌三首のうちの一首。
サ行の音の繰り返しが快く響く名歌である。
ここで、疑問が残る。石見国で妹と別れ上京するが、終焉の地も石見が有力とされている。謎多き人麻呂であるが、また1つ謎が増えた!
『柿本人麻呂(之)歌集』は、人麻呂が採集し、編纂したと考えれられ『万葉集』成立以前の和歌集。自身の歌も少なくないといわれる。
アラカシRhododendron kaempferi
| 万葉呼名/かし | 分類/ブナ科常緑高木 | 結実時期/秋~冬 |
「しなでる 片足羽川(かたあしがほ)の さ丹(に)塗りの大橋の上ゆ 紅の 赤裳裾引き 山藍もち
摺れる衣着て ただひとり い渡らす児は 若草の 夫(つま)かあるらむ 橿の実の
ひとりか寝らむ 問(と)はまくの 欲しき我妹(わぎも)が 家の知らなく」高橋虫麻呂(巻九・一七四二)
*片足羽川の赤く塗った大橋の上を紅の裳裾を長く引いて山藍で摺り染めた衣を着て、たったひとりで渡って行く子は、若々しい夫があるだろうか。寝るときは独りなのだろうか。問いかけてみたい愛しい子だけれど、住む家を知らない。

果実は堅果(ドングリ)。この歌は近畿内で歌われており、
このかし(樫)は西日本に多いアラカシと思われる。
愛おしい若い女性の独り寝を、
コロリとしたアラカシの実に例えて詠んでいる。
高橋虫麻呂(たかはしのむしまろ)は生没年不明の奈良時代前期の万葉歌人。天平期(729~749)の初め、朝廷に仕え、後年は地方官として東国に下り、常陸国(現在の茨城県)に住んでいたと推定される。このころ、常陸国国守藤原宇合(うまかい)の下僚として、『常陸国風土記(ふどき)』の編纂(へんさん)にも関与したらしい。
題詞「勝鹿(かつしか)の真間(まま)娘子を詠める歌一首并せて短歌」
「勝鹿の 真間の井見れば 立ち平(なら)し 水汲(く)ましけむ 手児奈(名・てこな)し思ほゆ」(巻9-1908)
長歌で下総国葛飾郡(現在の千葉県市川市)の伝説を物語的に歌い、短歌で手児奈を偲んでいる。勤め先が常陸国であれば、非番の日にはぷらりと下総まで足を延ばしたのであろうか。
『万葉集』には長歌14首、短歌19首、旋頭歌(せどうか)1首、計34首を残している。
クズPieris japonica subsp. japonica
| 万葉呼名/くず | 分類/マメ科蔓性植物 | 開花時期/9月~ |
「足柄の 箱根の山に 延ふ葛の 引かば寄り来ね したなほなほに」防人(巻一四・三三六四)
*「足柄の 箱根の山に 粟(あわ)蒔きて 実とは成れるを 粟無くもあやし」―足柄の箱根の山に粟を蒔き実を結んだのに、恋人に「あわ」ないのはどうしたことか―(巻14-3364)の或本(あるまき)歌 葛の根を引き抜くように、私がお前を引き寄せたら寄っておいで。


クズの花
(出典:「城西国際大学 薬草写真集第5巻」より)
山野に生い茂るクズの花は甘い香りを漂わせる。名前は奈良県の国栖(くず)が、葛粉の産地だったことから。地下茎(葛根)を漢方で風邪薬に用いる。蔓(つる)は編んで籠を作るほか、発酵させたあとの繊維で葛布(くずふ)を織るなど生活に欠かせない植物だ。蹴鞠(けまり)の装束の袴は、この葛布で作られているそうだ。『万葉集』には18首詠まれているが、その多くは所嫌わず生育して広がるたくましさを歌いあげている。
防人(さきもり)とは大化改新後、北九州の防備にあたった兵士。初め諸国の兵士の中から3年交代で選ばれ、のちに東国出身者に限られるようになった。『万葉集』には、第13巻、第14巻、第20巻に防人の歌が収録されており、特に第20巻には「天平勝報宝七歳乙未二月、相替へて諸国に遣葉さるる防人等が歌」と題して、80数首が載せられている。防人らの歌の半分が愛する恋人や妻、父母を詠んでいる。
注:或本「あるまき」と読む。『万葉集』の編纂時に少しことばの違う歌が載ってい別の本のこと。
葛も粟も番号が同じで詠まれているので、4516首とも4536首とも言われる所以であろうか。